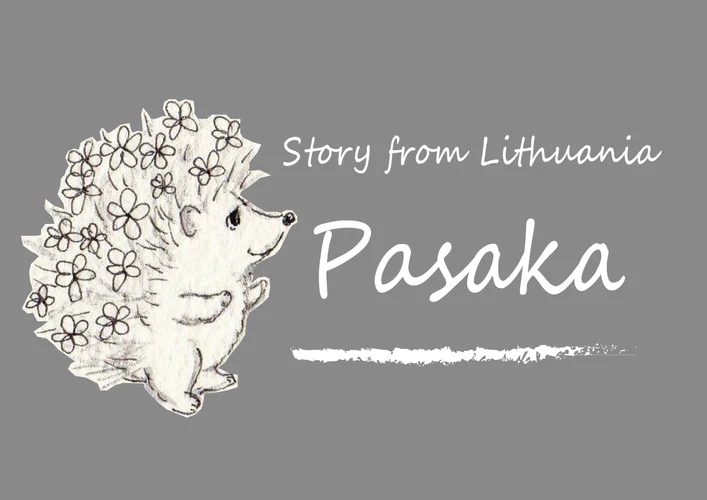はちみつの歴史と健康効果

はちみつの歴史は人類の歴史であり、最も古いスーパーフードです。はちみつは、良質なビタミンやミネラルをはじめ、アミノ酸やさまざまな酵素といった栄養素の種類が豊富に含まれています。最も古いスーパーフードと言っても間違いではないでしょう。事実、その歴史は大変古く、石器時代に人が住んでいたと考えられているスペイン・アラーニャの洞窟には、はちみつを集める女性の姿が描かれた岩絵があります。
描かれた時期は、紀元前1万5000年頃とも紀元前6000年頃とも言われますが、いずれにせよ人間とはちみつには長い歴史があることは間違いありません。イギリスには「The history of honey is the history of mankind.(はちみつの歴史は人類の歴史)」という古いことわざがあります。その後、私たちの祖先は野生のミツバチからではなく、ミツバチを育て、その巣からはちみつを取る方法を見つけ出しました。養蜂(ようほう)です。古代エジプトの壁画には、ミツバチの巣箱からはちみつを取り出している養蜂の様子が描かれています。
日本のはちみつの歴史は飛鳥時代からです。日本の歴史に、はちみつや養蜂が登場するのは飛鳥時代の643年です。『日本書紀』の中に「百済の太子余豊、蜜蜂の房四枚をもって三輪山に放ち、養う。しかれどもついに蕃息(うまわ)らず」と書かれているのです。意味は、百済(現在の朝鮮半島)から来た余豊という人物が、三輪山で養蜂を試みたが上手くいかなかったというものです。
その後、奈良時代には、はちみつが朝廷への貢物として献上された記録が残っていますが、養蜂が本格的に行われるようになったのは江戸時代になってから。寛政3年(1791年)に二ホンミツバチの生態や養蜂技術を記した『家畜蓄養記』という本が書かれました。明治時代には、セイヨウミツバチが輸入されるなど、養蜂も近代化を迎えました。
そして現在、養蜂を取り巻く環境は決して優しいものではありません。ミツバチが蜜を集めることができる自然環境が少なくなってきているのです。農林水産省のデータによると、平成26年(2014年)のはちみつの流通量は約4万トン。そのうち国内の生産量は約2800トンで、自給率は7%に留まります。およそ30年前、昭和60年(1985年)は、消費量3万5000トンのうち、生産量は約7000トン以上あり、自給率は20%を超えていました。
近年、国産はちみつやビルの屋上緑地などを活用した都市部での養蜂などへの関心の高まりから、ミツバチの飼育個数は増加傾向にあります。
サクラ、ミカン、リンゴなど、日本のはちみつの蜜源です。日本国内には600種類以上、世界には約4000種の蜜源があると言われています。日本国内の代表的な蜜源には、「サクラ」、「ナタネ」、「レンゲ」、「ミカン」、「アカシア」、「クローバー」、「リンゴ」、「トチ(マロニエ)」、「ソバ」などがあります。
アカシアの淡いピンクの花からできたアカシア蜜はほぼ透明で、淡い色をしています。レンゲの花のはちみつはアカシアよりも少し色が濃く、そして、そばの花から採れるはちみつは黒に近い濃い色になります。
オレンジ、ひまわり、ローズマリーなど、世界のはちみつの蜜源
山田養蜂場のホームページでは、代表的な世界のはちみつが紹介されています。例えば、カナダのクローバー、メキシコのオレンジ、中国のレンゲ・菜の花、ニュージーランドのマヌカ、ルーマニアのひまわり・アカシア、スペインのローズマリーなどの蜜源がよく知られています。
ハニーデューなど、ユニークな蜜源です。またユニークな蜜源としては、ハニーデューがあります。これは花でなく、さまざまな木からでる樹液からつくられるはちみつ。ミツバチが直接樹液を集める場合もありますが、昆虫の中には樹液を吸った後、糖分を体の外に出して、木の幹や葉に水滴のようにつける種類がいます。それらは「甘露」と呼ばれます。この甘露をミツバチが集めたものが「甘露はちみつ」になります。
はちみつに含まれる成分
はちみつの成分は、糖分が約80%、残り約20%は水分です。この80%という高い糖分は、ミツバチが花の蜜を集めただけでは生まれません。元々、花の蜜は水分が多く、糖度が低いため巣の中で腐りやすいため、保存食には適していません。そのためミツバチは巣内に蜜を広げたり、羽で羽ばたいて水分を飛ばし、糖度を80%まで上げているのです。
花の蜜の成分であるショ糖は、ミツバチが持つ酵素によって、ぶどう糖と果糖に分解されます。そしてさらに、はちみつにはビタミン、ミネラル、アミノ酸、有機酸、酵素などさまざまな天然成分が含まれています。その種類は、約300種類とも言われています。ただし、蜜源植物により成分は異なります。
はちみつの健康効果
「はちみつの歴史は人類の歴史」ということわざ通り、私たちの祖先は古くから、はちみつのさまざまな健康効果を活用してきました。古代エジプトや古代インドのアーユルヴェーダ、イスラム教のコーランにも、はちみつの効能が書かれています。さらに古代ギリシャの医学者で、西洋医学の父とされるヒポクラテスもはちみつの効能を述べています。はちみつの健康効果
はちみつの健康効果 その1:殺菌作用
代表的な効能として、今ではあまり意識することはありませんが、はちみつはその強い殺菌作用が傷の治療などに使われてきました。はちみつは80%という高い糖度を保っているため、細菌が繁殖できません。はちみつにはブドウ糖由来の過酸化水素(別名オキシドール)が含まれていることも、殺菌力の高さの所以です。グルコースオキシターゼという酵素が含まれていて、水が加わるとさらに過酸化水素が発生します。そのため強い殺菌作用を発揮します。この過酸化水素は消毒液に含まれる成分です。
これは、巣の中に蓄えられたはちみつが、何らかの原因で水分を吸って糖度が下がったときのための、防衛策。糖度が下がって、細菌が繁殖しやすくなったはちみつを守るために、はちみつに含まれる酵素が過酸化水素を発生させるのです。自然の仕組みには驚かされます。さらに、はちみつには傷を殺菌するだけでなく、早く治す効果もあるとされています。
はちみつの健康効果 その2:整腸作用
はちみつは古くから下痢や便秘の薬として使われてきました。つまりは腸の働きを整える作用があるのです。はちみつに含まれるグルコン酸やオリゴ糖は、腸内の善玉菌を増やします。腸内環境を整えることは、腸でつくられるさまざまな免疫の働きを整えることにつながり、大腸がんの予防にもつながります。
はちみつの健康効果 その3:疲労回復
はちみつは元々、ミツバチの大切な栄養源。はちみつの主成分である、ぶとう糖(グルコース)、果糖(フルクトース)は非常に吸収されやすい糖なので、疲労回復には最適です。
はちみつの健康効果 その4:免疫力アップ、生活習慣予防、アンチエイジングなど
その他、はちみつに含まれる数多くのビタミン、ミネラル、アミノ酸、有機酸、酵素などは、免疫力アップや生活習慣病予防、抗酸化作用、アンチエイジングに効果があるとされています。